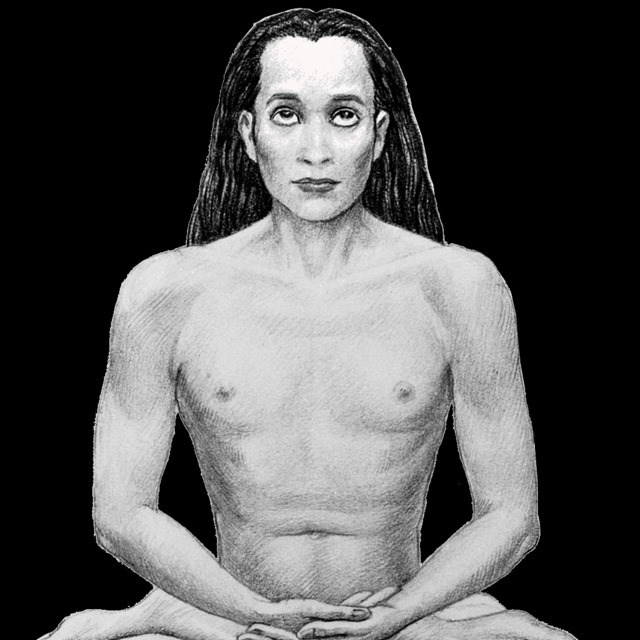【政策要旨】請願2.0による起案制度の創設に関する法案について
【1】請願1.0成立の背景と請願2.0の制度的意義
請願1.0は、現行制度の形式的限界に加え、立法機能における深刻な構造的欠陥を背景に生まれた。
現在、議員が掲げる政策の多くは、選挙スローガンとして提示されるに過ぎず、制度的に担保される根拠を持たない。
有権者が政党や候補者の政策に基づいて投票したとしても、その公約が制度的に履行される保証は存在せず、
公約不履行による法的制裁も設けられていない。
さらに、実際の制度改正は、複数の法律・政省令・行政運用・財源構造等を横断的に理解したうえで制度設計を行い、法案に落とし込む高度な作業を要する。
制度的にも、議員個人が単独で制度改正を実行する権限は限定的であり、複数の法令や予算措置を横断的に調整するためには、議会内の合意形成や政党間調整を要する構造となっている。
加えて、現実には多くの議員が、制度設計を含む法案を自らの手で構築・起草するだけの法的リテラシーや技術的能力を有していないという実務上の問題が存在する。
このような現状において、抜本的な制度改革を伴う政策(例:消費税の構造改革)は、政治的主張として表明されることはあっても、制度的には実現に至らない構造となっている。
こうした限界の中で、制度設計・立法構造・憲法・財政法に至るまで国法全体を理解した上での法案起草が不可避となり、
やむなく請願者が高い法的リテラシーに基づいて、制度提案および法案起草を代筆するに至ったのである。
すなわち、請願2.0とは、代議制の限界を見極めた上で、市民自らが立法的責任を担う新たな民主主義の制度的提案である。
【2】従来の請願制度における問題点
日本の現行請願制度は、国民が議会に対して意見や要望を伝える手段として長い歴史を持つが、以下の構造的課題を抱えている。
一 国会において請願は受理されても審査される義務がなく、ほとんどの請願が形式的に処理され、実質的には黙殺されている
二 提出された請願書の内容は、請願の件名・請願者名・紹介議員名が広報に短く掲載されるのみであり、議員には請願書本体や資料の詳細が共有されない
三 議員が請願の詳細を確認したい場合であっても、所属委員会に申請し、紙面での配布を受けるという極めて非効率かつ閉鎖的な運用となっており、国民からの声が議会に届かない構造となっている
四 提出された請願書を閲覧するためには、原則として国立国会図書館に赴き、紙媒体を確認する他に方法がないという、時代錯誤な情報非公開状態にある
五 紹介議員の存在が制度的に必要とされているが、実際には議員が請願の内容を精査する機会すら持たないまま、形式的に紹介を行う例が大半である
六 制度的にも、内容的にも「苦情」「陳情」としてしか扱われないため、建設的な制度提案や法案提示を含む請願が制度的に受け止められる余地が極めて小さい
【3】請願1.0(法案提示型請願)の成果と限界
現行制度下においても、制度の枠を越える先駆的な試みが行われた。
特に「真・消費税改革法案」は、制度の限界を突き破る以下のような重要な実績を挙げており、本法案(請願2.0)の制度化に向けた強固な前例となっている。
【成果1】紹介議員なしでの衆議院広報掲載の実現
広報発行日:2025年6月16日
掲載号:第217回国会 第97号(6月16日発行)
紹介議員不在にもかかわらず、正式な請願として衆議院広報に掲載されたことは、制度上極めて異例の対応である。
これは、「内容の整備された請願」であれば、制度的ハードルを越えて議会に届き得るという前例である。
【成果2】制度的境界を突破する市民立法活動の証明
本請願は、苦情の表明にとどまるものではなく、制度設計、法案草案、解説資料等を包括的に整備した立法提案として構成されていた。
このような構成を有する請願が、議会において一部とはいえ受理され、広報に掲載された事実は、立法提案型請願が制度上一定の実効性を持ち得ることを示す重要な先例である。
【限界1】請願内容は非公開・審査されず
広報に掲載されたのは請願名・請願者名等の最低限情報にとどまり、請願書の中身や資料は議員にも国民にも開示されなかった。
議員が内容を確認するには、委員会を通じて紙面配布を申請する必要があり、非常に非効率な構造であった。
【限界2】正式な審査・起案に至らず
請願が制度的に記録されたにもかかわらず、その後の起案・議案化・審査には至らなかった。
これにより、市民が整えた法案が国会内で議論されることなく、制度外で停滞する結果となった。
このような成果と限界を踏まえ、制度的に起案・審査が義務化される新たな請願制度(請願2.0) を創設することが、喫緊の課題である。
【限界3】議員による起案拒否・無視の常態化
本請願は、広報に掲載された後、複数の国会議員に対し、法案としての起案を求める要請が直接行われた。
しかしながら、議員はいずれもこの請願内容を取り上げることなく、制度的にも政治的にも黙殺される結果となった。
この事実は、制度の形式的受理にとどまらず、実質的に立法府が市民からの制度提案を扱う意志を欠いている現状を示すものであり、
請願制度における「審査義務」「起案責任」の明文化が不可欠であることを強く裏付けるものである。
【4】請願2.0の意義と制度設計
請願2.0は、これらの限界を克服し、以下の要件を備えた市民主体の立法起案モデルである。
【要件】
一 請願の目的と制度的意義を明記した政策要旨が整備されていること
二 現行制度の課題と解決策を構造的に記述した政策提案書が添付されていること
三 新設または改正を求める法案が、条文形式で草案化されていること
四 当該法案の趣旨・意図・影響分析等を記載した法案解説資料が添付されていること
五 署名および支援に関して、次のすべての要件を満たしていること
(一)署名者は個人情報(氏名・連絡先等)の記載を要しない。ただし、各署名者が500円の固定支援金を支払うことで署名行為を代替する形式とし、当該支援金の総額をもって署名者数(支援金総額÷500円)を推計することができる。これを証明するために、支援金受領記録(例:PayPalの入金明細)を提出すること
(二)署名者とは別に、SNS等のオンラインプラットフォーム上において、当該請願に対する賛同を表明した利用者(いいね等による支持)が八万人以上存在すること
(三)上記(二)の賛同については、請願公開ページにおける記録・集計が閲覧可能であり、誰でも確認できる状態にあること六 請願書および関連文書が、Web上で一般に公開されており、誰もが閲覧・検証可能であること
七 当該様式をすべて満たしている旨が明示された請願書が提出されていること
この様式を満たす請願を「請願2.0」として制度化することで、国会は以下の義務を負う。
- 起案・審査の実施
- 起案しない場合には、その理由の明示または対案の提示
- 審査過程を国民に対して透明化する情報公開義務
【補足条項】支援金の帰属および目的
請願2.0における支援金は、請願の制度設計・提案書作成・法案整備・資料公開等に係る費用を市民が共同で負担する制度的な参加金である。
この支援金は、請願の提出および起案活動を実施した請願者に帰属するものとし、請願活動の自由と独立性を保障する財政的基盤として制度的に認められる。
【5】本法案の目的
本法案は、上記「請願2.0」の制度的枠組みを国会法その他関連法令に位置付け、
それに該当する請願に対して、国会が起案・審査の責務を負うことを明確化することを目的とする。
また、制度創設以前に提出された請願であっても、その内容が「請願2.0」の要件を充足している場合には、
本制度の適用対象とし、起案・審査の対象として復活させる。